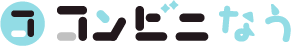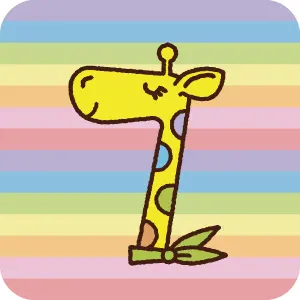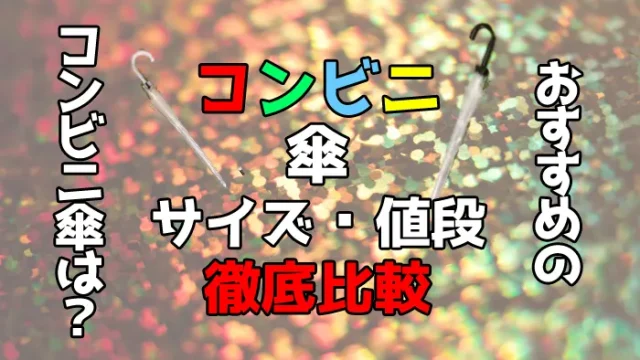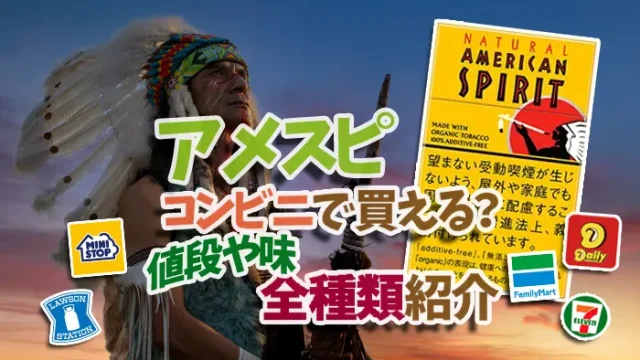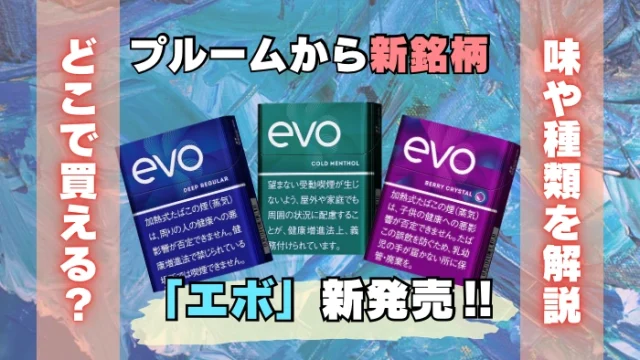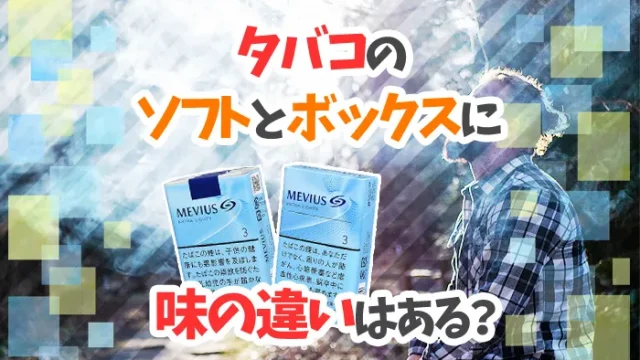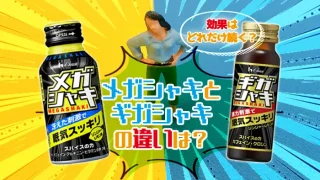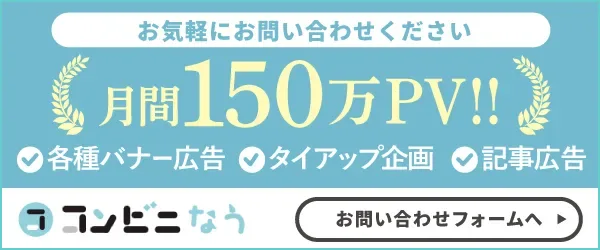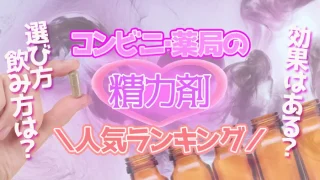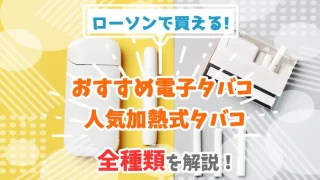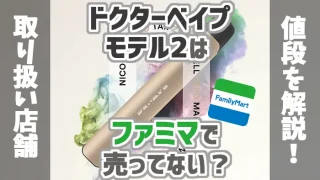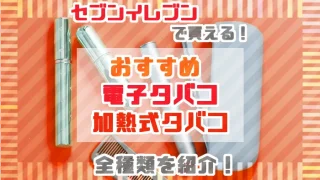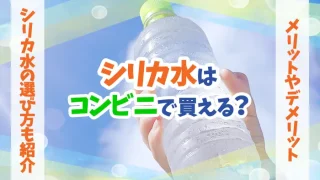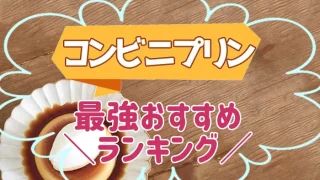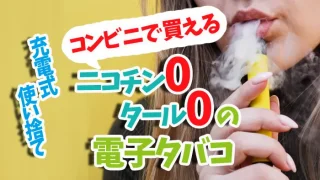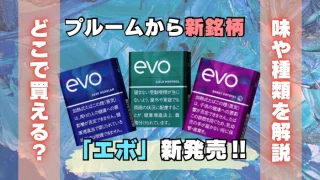大晦日の夕食や夜食の定番として多くの方に親しまれている年越しそばですが、なぜ食べるのでしょうか。
結論から言うと、大晦日の夕食や夜食として年越しそばを食べるのは、災厄を翌年に持ち越さないためであると言われています。
当記事では年越しそばをなぜ食べるのか、その由来・意味やいつ食べるのかを解説すると共に、地域によって特徴が異なるさまざまな年越しそばをご紹介していきます。
目次
年越しそばを大晦日に食べる主な理由は「災厄を翌年に持ち越さないため」

年越しそばをなぜ食べるのか、その主な理由は「災厄を翌年に持ち越さないため」であると言われています。
そばは細長いことから「健康で長い間生きられるように」切れやすい性質から「今年1年の苦労や不運を切り捨てる」といった願いを込めて大晦日に食べられます。
1年間の締めくくりとしてさまざまな願いが込められた年越しそばを食べることで、災厄を持ち越さず新年を気持ちよく迎えられるでしょう。
年越しそばをなぜ食べるのか由来や意味を解説

ここまで、年越しそばを大晦日に食べる主な理由は「災厄を翌年に持ち越さないため」であると解説してきました。
年越しそばには災厄を翌年に持ち越さないという意味以外にも、さまざまな由来や意味が込められており、それらを知ることでより年越しそばを楽しめるようになります。
ここでは、年越しそばをなぜ食べるのか、その由来や意味を5つご紹介していきますのでぜひ参考にしてみてください。
- 災厄を断つ「縁切りそば」
- 長寿を願う「寿命そば」
- 健康を願う「健康そば」
- 金運上昇を願う「福そば」
- 運気上昇を願う「運気そば」
由来や意味①:災厄を断つ「縁切りそば」
年越しそばをなぜ食べるのか由来や意味の1つ目は、そばが切れやすいことからきた、災厄を断つ「縁切りそば」という意味です。
そばは他の麵類と比べて切れやすい特徴を持っており、年越しそばには「1年間の災厄や苦労を切り捨てて翌年に持ち越さない」という願いが込められています。
年越しそばの別名である「縁切りそば」は悪いものと縁を切って、気持ちよく新年を迎えたいという気持ちから名付けられています。
由来や意味②:長寿を願う「寿命そば」
年越しそばをなぜ食べるのか由来や意味の2つ目は、細くて長い麺であることからきた、長寿を願う「寿命そば」という意味です。
そばは麵類の中でも細くて長いことから延命や長寿を祈願して食べられることが多く、引っ越しの際に送る「引っ越しそば」にも長いお付き合いという意味が込められています。
大晦日に年越しそばを食べることは、翌年以降も長い間健康で生きられますようにという意味が込められています。
由来や意味③:健康を願う「健康そば」
年越しそばをなぜ食べるのか由来や意味の3つ目は、原料であるそばの実からきた、健康を願う「健康そば」という意味です。
そばの原料であるそばの実は、激しい雨風を受けてもその後の晴天ですぐに元気になるという特徴があり、人間の健康を願う食材としても親しまれています。
大晦日に年越しそばを食べることによって、翌年は今年受けた苦労や災厄から復活して元気に過ごせるようにという願いが込められています。
由来や意味④:金運上昇を願う「福そば」
年越しそばをなぜ食べるのか由来や意味の4つ目は、そば粉の昔ながらの使い方からきた、金運上昇を願う「福そば」という意味です。
そば粉は金粉や銀粉を集めたり金箔を延ばす用途で使われていた歴史があり、そばは金を集める縁起物であると考えられています。
大晦日に年越しそばを食べることには、来年もお金を稼いでたくさんの金が手元に集まるようにという意味が込められています。
由来や意味⑤:運気上昇を願う「運気そば」
年越しそばをなぜ食べるのか由来や意味の5つ目は、そば餅を食べた人が運気アップしたことからきた「運気そば」という意味です。
鎌倉時代には福岡県博多のお寺で貧しい人々に「世直しそば」というそば餅を配る習慣があり、世直しそばを食べた人は翌年から運気が上がるとされていました。
実際に運気が上昇したと感じる人が多かったことから、そばを縁起物と考える習慣が全国に広まり、年越しそばを食べる習慣に繋がったと言われています。
年越しそばはいつ食べるのが正しいかを解説
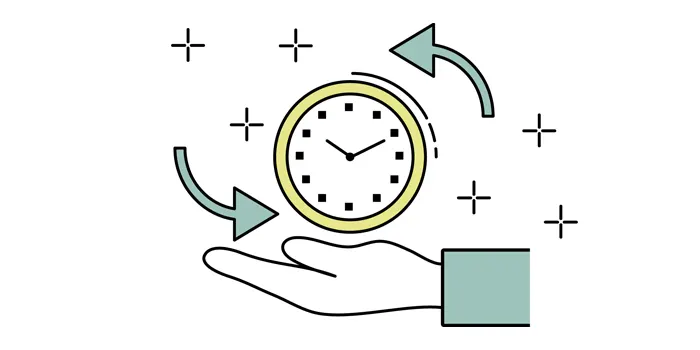
ここまで年越しそばを食べる由来や意味として「縁切りそば」「寿命そば」「健康そば」などさまざまなものがあることを解説してきました。
では、そのように縁起の良い年越しそばは「大晦日の夕食として食べる」「ちょうど年を越すタイミングで食べる」など、いつ食べるのが正解なのでしょうか。
ここでは、年越しそばを食べる際大晦日のいつに食べるのが正しいのか、地域によって違いがあるのかどうかなどを解説していきます。
決まりはないが日付が変わる前に食べるのが一般的
年越しそばはいつ食べるのが正しいのか、特に決まりはありませんが、日付が変わる前に食べるのが一般的となっています。
年越しという言葉から午後11時過ぎくらいに除夜の鐘を聞きながら年越しそばを食べるという家庭も多いですが、夕食として夕方に済ませてしまう家庭も少なくありません。
年越しそばを食べるのに正しい時間というのは決まっていないため、大晦日のどこかで食べられれば良いと気軽に考えていても問題ないでしょう。
夕食や夜食として年越しそばを食べる家庭が多い
年越しそばを大晦日のいつ頃に食べるのか、統計を取った結果としては夕食や夕食後の夜食として年越しそばを食べる家庭が多い傾向にあります。
大晦日の夜は翌日食べるおせちの準備やテレビの大晦日特番などで忙しい場合も多く、夕食として年越しそばを食べている家庭が約半数となっています。
一方で、大晦日だけは夜更かしをして年越しを迎えるという家庭も多いので、夜中にお腹が空いたタイミングで夜食として年越しそばを食べるパターンも一般的です。
地域によっては昼や年明けに食べる風習がある
大晦日に食べられることが多い年越しそばですが、東北地方の一部地域などでは昼間や年明けに食べられる場合もあります。
福島県会津地方の一部地域ではお正月の縁起の良い食べ物としてそばを食べ、大晦日には年越しそばではなく福島の郷土料理を食べるというのが習わしです。
他にも新潟県の一部地域では、大晦日ではなく小正月の前日である1月14日に年越しそばを食べることもあります。
年越しそばにおすすめの縁起の良い具材をレシピと共にご紹介

ここまで、年越しそばを食べる由来や意味、大晦日の何時頃に食べるのが正しいのかを解説してきました。
では、実際に年越しそばを作る場合、どのような具材を使ってどんなレシピで作るのが縁起が良いとされているのでしょうか。
ここでは、年越しそばにおすすめの縁起の良い具材をレシピと共に3種類ご紹介していきますので、ぜひ参考に大晦日の年越しそばを作ってみてください。
- 海老
- ネギと鶏
- 春菊と卵
具材①:海老
年越しそばにおすすめの縁起の良い具材1つ目は、不老不死の象徴とされている海老です。
海老はひげが長くて腰が曲がった老人のような見た目をしており、この見た目になぞらえて「ひげが長く伸びるまで、腰が曲がるまで長生きするように」という願いの込められた具材です。
年越しそばには「寿命そば」という由来・意味があることから、翌年も健康に生きられるようにという願いを込めて年越しそばに海老を入れるのは縁起が良いとされています。
具材②:ネギと鶏
年越しそばにおすすめの縁起の良い具材2つ目は、さまざまな縁起の良い由来を持ったネギと鶏です。
ネギは「1年間の苦労を労う(ねぎらう)」という語呂合わせから縁起が良い具材とされており、鶏は「1年の1番最初に鳴く動物」であることから縁起が良いとされています。
さらに、年越しそばに鶏を入れれば出汁が出て美味しくなる、ネギを入れれば風味豊かなそばになるといった食味の観点からもおすすめの具材です。
具材③:春菊と卵
年越しそばにおすすめの縁起の良い具材3つ目は「繫盛」や「金運上昇」の意味がある春菊と卵です。
春菊はちょうど大晦日の頃に旬を迎えることから「繫盛」を意味し、黄身が金色を思わせる卵には「商売繫盛」や「金運上昇」といった意味があります。
年越しそばには「福そば」という意味・由来があることからも、翌年の金運の上昇や商売繫盛を願って春菊や卵を入れるのがおすすめです。
地域ごとの年越しそばの特徴を解説

ここまで、年越しそばには海老・ネギ・鶏・春菊・卵などの縁起が良いとされている具材を入れるのがおすすめであるとご紹介してきました。
さまざまな具材を入れて美味しく楽しむことのできる年越しそばですが、地域によってもそれぞれ違いや特徴があるとされています。
ここでは、日本全国7か所の地域で親しまれている特徴のある年越しそばをご紹介していきますので、自分の住んでいる地域の年越しそばを確認してみてください。
- 北海道や京都府の「にしんそば」
- 岩手県の「わんこそば」
- 新潟県の「へぎそば」
- 福井県の「おろしそば」
- 長野県の「くるみそば」
- 島根県の「釜揚げそば」
- 沖縄県の「ソーキそば」
特徴①:北海道や京都府の「にしんそば」
地域ごとの年越しそばの特徴1つ目は、北海道や京都府で親しまれている「にしんそば」です。
にしんの主な産地である北海道では古くからにしんを使ったにしんそばが親しまれており、にしんが多く運ばれてくる京都府においてもにしんそばが広まりました。
にしんを使っている点は同じであるものの、京都府が淡い色の薄口出汁を使用しているのに対し、北海道は濃口醬油を使った関東風の味付けであるといった違いがあります。
特徴②:岩手県の「わんこそば」
地域ごとの年越しそばの特徴2つ目は、郷土料理としても知られる岩手県の「わんこそば」です。
わんこそばはつるっと食べやすい少量のそばが椀子に小分けにされており、その椀子をおかわりして何杯食べられるのかを楽しむそばです。
「大晦日に年齢と同じ杯数のわんこそばを食べると長生きできる」という言い伝えもあり、岩手県には年越しそばとしてわんこそばを楽しむ「年越しわんこ」の習慣があります。
特徴③:新潟県の「へぎそば」
地域ごとの年越しそばの特徴3つ目は、器が特徴的な新潟県の「へぎそば」です。
へぎそばは「へぎ」と呼ばれる四角い器に入っていることが特徴で、麵には「布海苔(ふのり)」という海藻をつなぎに使ったものが使用されています。
へぎへ1口分ずつ丁寧に盛り付けられたそばは見た目が織物のように美しく、大晦日やお正月のお祝い事として食べるのにもぴったりです。
特徴④:福井県の「おろしそば」
地域ごとの年越しそばの特徴4つ目は、大根おろしであっさりとした福井県の「おろしそば」です。
大根おろしが使われた「おろしうどん」は日本全国で親しまれていますが、福井県ではそばを大根おろしとさっぱりした出汁で楽しむおろしそばが親しまれています。
あっさりとしているのでそば本来の風味が損なわれず、美味しいそばの味を最大限に楽しみたい方におすすめの年越しそばです。
特徴⑤:長野県の「くるみそば」
地域ごとの年越しそばの特徴5つ目は、くるみの豊かな風味が特徴的な長野県の「くるみそば」です。
くるみそばは麵にくるみが使用されているのではなく、つゆへ潰したくるみや味噌・砂糖を入れてごまだれのように楽しみます。
くるみの香ばしい香りとまろやかな味わいはそばとの相性がよく、くるみにはさまざまな健康効果も期待できるので、年越しそばの持つ「健康そば」という意味にぴったりです。
特徴⑥:島根県の「釜揚げそば」
地域ごとの年越しそばの特徴6つ目は、茹で上げたそばをそのまま食べる島根県の「釜揚げそば」です。
釜揚げそばは茹で上げたそばを茹で汁ごと器に盛り付け、そこにかつお節・ネギ・海苔などの調味料を乗せ、独特の甘くて濃い目のつゆを回しかけて食べます。
地元では、熱々の釜揚げそばに追加で冷たいそばを注文するという食べ方が楽しまれているので、ぜひ試してみてください。
特徴⑦:沖縄県の「ソーキそば」
地域ごとの年越しそばの特徴7つ目は、食べごたえのあるソーキがトッピングされた沖縄県の「ソーキそば」です。
沖縄県の郷土料理として親しまれているソーキそばには、豚のあばら骨を煮たソーキ(スペアリブ)や紅ショウガがトッピングとして盛り付けられています。
ソーキは食べごたえがあって満腹になるものの、出汁はさっぱりとしたカツオ出汁であることが多く、大晦日の夜食にも適しています。
年越しそばを大晦日に食べる由来や意味に関するQ&Aを3つご紹介

ここまで「年越しそばをなぜ食べるのか」「年越しそばはいつ食べるのが正しいのか」「地域ごとの年越しそばの特徴」などを解説してきました。
しかし、年越しそばについてここまでの解説にない疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、年越しそばについて「いつ始まったのか」「日本だけの風習なのか」「そばの代わりにうどんでも良いのか」といった疑問に回答していきます。
Q&A①:年越しそばの風習はいつ始まった?
まずは、年越しそばを大晦日に食べる由来や意味に関する質問1つ目「年越しそばの風習はいつ始まった?」について回答していきます。
年越しそばが始まった時期についてはいくつかの説がありますが、おおむね江戸時代の前期から中期頃ではないかと言われています。
当時作られた詩の中に年越しそばを題材に歌ったとされるものがあるので、年越しそばは江戸時代から長く続く風習であると言えるでしょう。
Q&A②:年越しそばを食べるのは日本だけ?
続いては、年越しそばを大晦日に食べる由来や意味に関する質問2つ目「年越しそばを食べるのは日本だけ?」について回答していきます。
結論から言うと、年越しそばを食べるのは日本だけです。国によって大晦日に食べられるものは異なり、それぞれに特徴があります。
具体的にはアメリカではコーンブレッド、キューバでは子豚の炭火焼、スペインではぶどう12粒など、日本以外の年越し文化を楽しんでみるのも良いかもしれません。
Q&A③:年越しそばの代わりに年越しうどんはあり?
最後は、年越しそばを大晦日に食べる由来や意味に関する質問3つ目「年越しそばの代わりに年越しうどんはあり?」について回答していきます。
そばが苦手であったりそばアレルギーである場合など、年越しそばを食べられない方もいるかと思いますが、その場合には年越しうどんでも全く問題ありません。
実際に近年では年越しうどんを食べる家庭も増えており、うどんが名物の香川県には紅白で彩られたうどんを年明けに食べる「年明けうどん」という習慣もあります。
年越しそばを大晦日に食べる由来や意味といつ食べるかの解説まとめ
年越しそばはなぜ食べるの?という疑問にお答えするため、年越しそばを食べる由来や意味、大晦日のいつ食べるのかについて解説してきました。
年越しそばは日本全国で親しまれている習慣ですが、地域によっては食べられるそばに違いがあったりと、奥の深い習慣でもあります。
縁起が良い具材を入れて楽しむことはもちろん、自分が住んでいる地域以外のそばを作ってみるなど、大晦日の年越しそばを自由に楽しんでみてください。