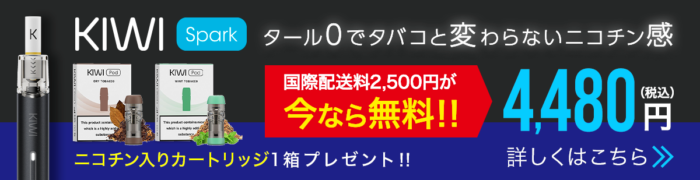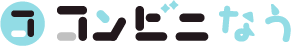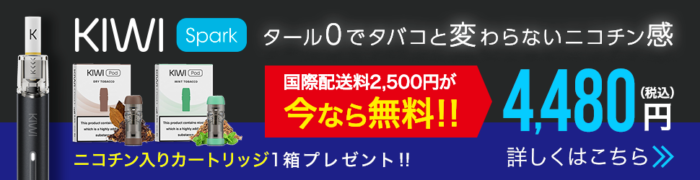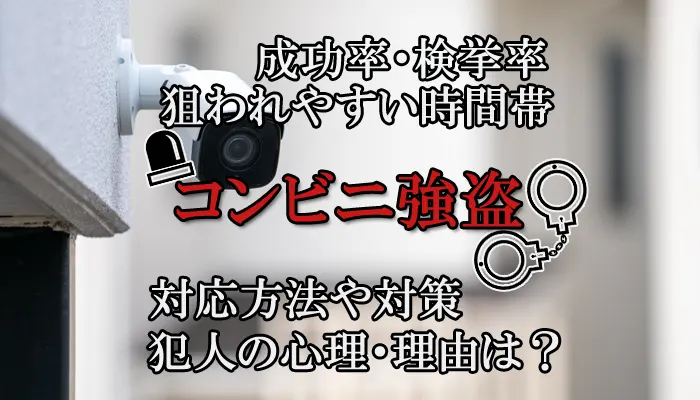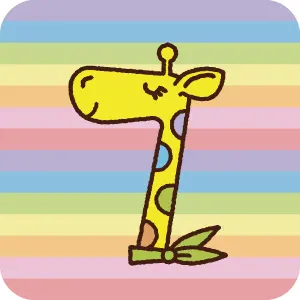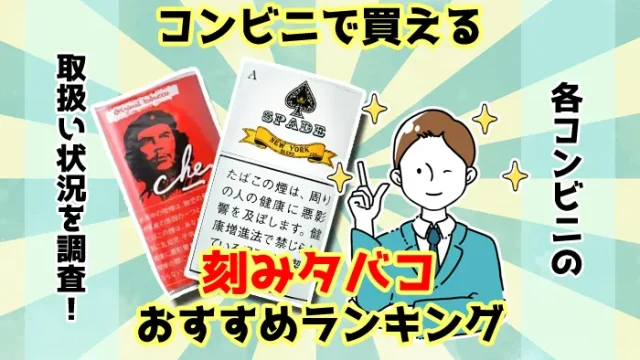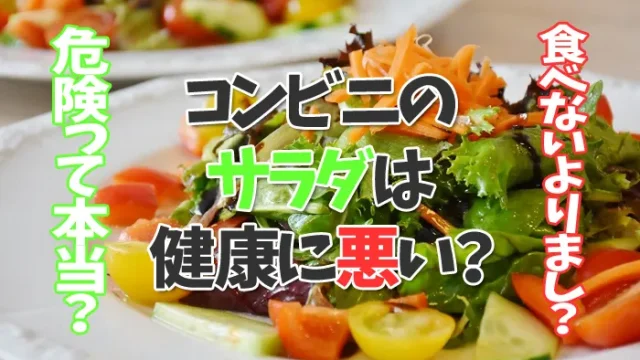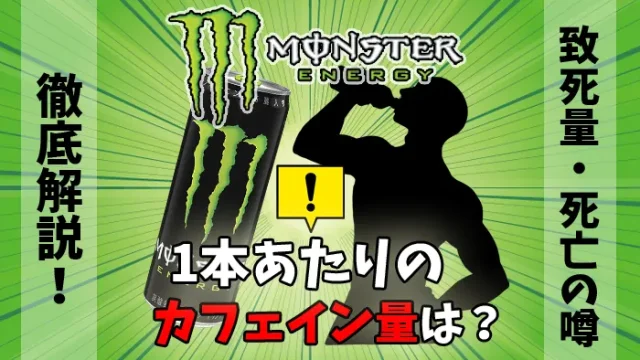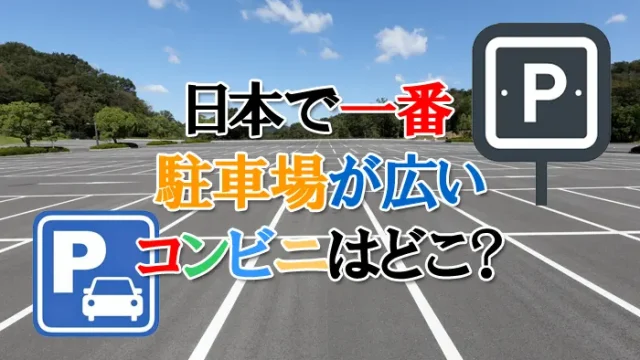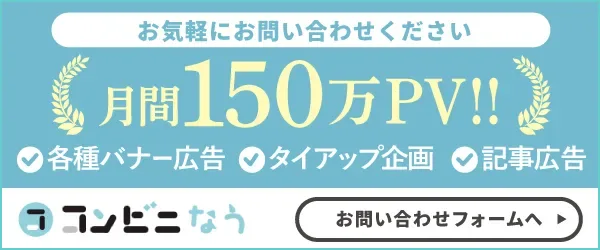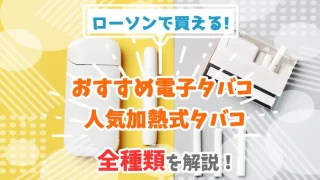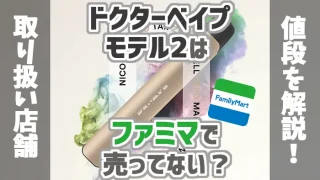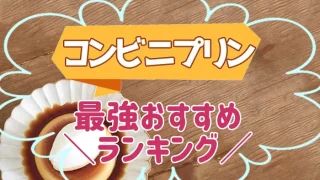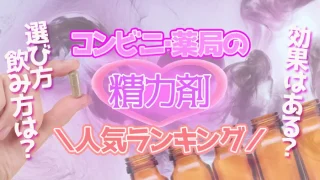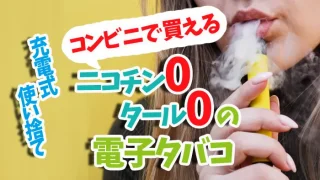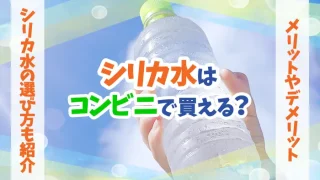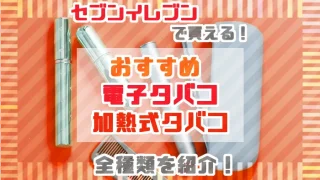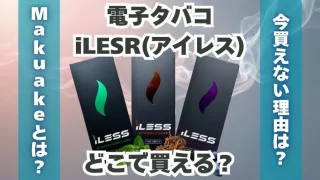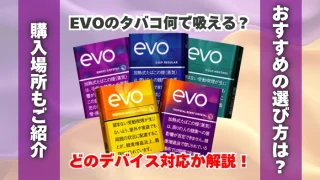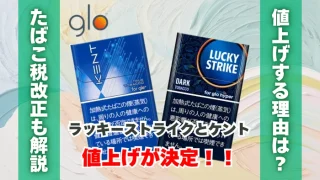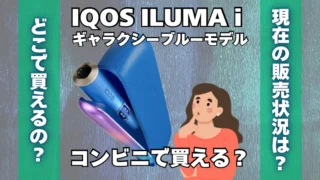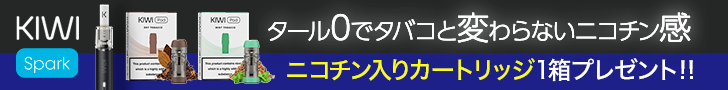コンビニは全国各地で24時間営業していることもあり、時には「コンビニが強盗被害に遭った」というニュースを目にすることもあります。
強盗を考えている人がどんなタイミングで実行に移しやすいのか、どうすれば被害を未然に防げるのかが知りたい方も多いはずです。
そこで本記事では、コンビニ強盗の成功率や強盗が狙う時間帯、対応方法や対策について詳しく解説します。
コンビニ強盗を実行した犯人の心理や理由なども合わせて解説しているので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
目次
コンビニ強盗の成功率・狙う時間帯や発生件数を徹底解説

セブンイレブン・ファミリーマート・ローソンなど、全国のコンビニで強盗被害に遭ったというニュースが稀に聞かれます。
強盗犯はどういった時間帯を狙って行動するのか、発生件数が増えているのか減っているのかが気になる方も多いでしょう。
まずは、コンビニ強盗の成功率・狙う時間帯や、発生件数について詳しく解説していきます。
コンビニ強盗は店員の数が少ない深夜から早朝の時間帯を狙ってくる
コンビニ強盗は対応する店員の数が少ない傾向にある、深夜から早朝の時間帯を狙ってくることが多いようです。
店舗にもよりますが、特に深夜から早朝の時間帯は人手不足などの理由から、店員がワンオペで運営していることも少なくありません。
たとえ男性の店員でも、凶器を出されたら身動きできなくなるのが普通なので、ワンオペは防犯の面で言うと絶対に避けるべき状況とも言えます。
コンビニ強盗の検挙率・逮捕件数が高いので発生件数自体は減少傾向にある
コンビニ強盗の検挙率は高く逮捕件数も多いことから、強盗の発生件数自体は減少傾向にあるようです。
例えば、コンビニ強盗の発生件数のピーク時である2009年は800件近く発生していたところ、2017年には約200件と大幅に減少しています。
一時的に得られるお金と逮捕されるリスクを考えた時に、実行するのは割に合わないと考える人間が多くなったのではないでしょうか。
コンビニ強盗は防犯カメラの設置件数が増加したことで犯人を特定しやすくなった
コンビニの防犯カメラを増やすことで店舗のセキュリティが強化され、犯人を特定しやすくなったことも強盗発生件数の減少に貢献しているようです。
例えばコンビニの店舗には、お店の出入り口からレジ・トイレ・バックヤード・駐車場や周辺道路まで、死角が生まれないように防犯カメラを設置しています。
防犯カメラ自体の性能も向上しており画質や音質が良くなったため、犯人の特徴をより詳しく特定しやすくなったことも検挙率が高い理由のひとつと言えるでしょう。
セルフレジの導入店舗件数が増えてコンビニ強盗がお金を盗みにくくなっている
強盗犯のよくある手口として、店員を凶器で脅してレジのお金を出させる場面をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、最近では無人で商品の会計が済ませられるセルフレジの導入店舗が増えたため、強盗がお金を盗みにくい環境に変わりつつあります。
有人レジを開けさせるのとは違い、セルフレジの機械の中を開けさせようとするケースは少ないことから、実質的な強盗対策にもなっているようです。
コンビニ強盗を撃退するための対応・対策を6つご紹介

コンビニの売り上げや店員の命を守るためにも、強盗を撃退するための対応・対策は抜かりなく済ませておきたいところです。
ここからは、コンビニ強盗を撃退するための対応・対策を6つに分けて紹介していきます。
複数の対応策を同時に実施することで強盗を未然に防ぎ、事件を早急に解決できるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。
コンビニ強盗撃退の対応・対策①:監視カメラを設置して犯人を特定しやすくする
コンビニ強盗撃退の対応・対策1つ目は、監視カメラを設置して犯人を特定しやすくすることです。
強盗発生時に警報ベルを鳴らしたり、自動で通報できる機能が付いた防犯カメラもあるので、設置することで強盗を未然に防ぐことも期待できます。
また未然に防ぐという意味では、録画機能のないダミーの防犯カメラを増やすことで犯人にプレッシャーを与えるのも効果的でしょう。
コンビニ強盗撃退の対応・対策②:カラーボールなどの防犯グッズを客から見える所に置く
コンビニ強盗撃退の対応・対策2つ目は、カラーボールなどの防犯グッズを客から見える所に置いておくことです。
カラーボールは、強盗犯に投げつけて匂いや塗料で目印をつけるといった効果がありますが、レジの中ではなくあえてお客さんから見える場所に置いておくという店舗もあります。
防犯カメラと同じように、強盗を考えている人間への抑止力にもつながるので、カラーボールの置き場所も工夫してみてはいかがでしょうか。
コンビニ強盗撃退の対応・対策③:強盗に狙われやすい時間帯の従業員数を増やす
コンビニ強盗撃退の対応・対策3つ目は、強盗に狙われやすい時間帯の従業員数を増やすことです。
ワンオペにしてしまうと、強盗犯に脅された際に店員さんが通報したり、何らかの対策を行うこともできなくなってしまいます。
店員の数が増えれば、強盗などの犯罪トラブルに万が一巻き込まれた際でも手分けして対応できるため、解決までの時間が短縮できる上に強盗を未然に防ぐこともできるでしょう。
コンビニ強盗撃退の対応・対策④:声かけを徹底して強盗に心理的プレッシャーを与える
コンビニ強盗撃退の対応・対策4つ目は、声掛けを徹底して強盗に心理的プレッシャーを与えることです。
入店時に大きな声で「いらっしゃいませ」と声を掛けることで、強盗を考えている人に「顔を見られてしまった」とプレッシャーを感じさせることができます。
元気のいい声掛けは強盗を考えている人への威嚇になり、未然に強盗を撃退することにも繋がるので、声掛けを店員に浸透させることも強盗対策として有効なのではないでしょうか。
コンビニ強盗撃退の対応・対策⑤:警察官立ち寄り所にしてもらう
コンビニ強盗撃退の対応・対策5つ目は、警察官立ち寄り所にしてもらうことです。
警察官にパトロールの一環としてコンビニに立ち寄ってもらうことで、強盗に狙われにくい環境に変わっていくでしょう。
実際に、大阪府警ではコンビニへの立ち寄り警戒を強化するため、警察官がパトロール中にコンビニで飲食物・物品を購入することを認めています。
コンビニ強盗撃退の対応・対策⑥:被害を最小限にするためにレジに大金を入れない
コンビニ強盗撃退の対応・対策6つ目は、被害を最小限にするためにレジに大金を入れないようにすることです。
強盗犯に凶器で脅された場合は、レジに入っているお金を全額を渡してしまうケースがほとんどなので、レジに大金が入っていると被害額も大きくなります。
レジに入れておく金額の上限をあらかじめ決めておき、超過している分はシフトが変わるタイミングで金庫に移すといった対策が有効的でしょう。
どうしてコンビニ強盗をするの?強盗をする3つの心理・理由を徹底解説!

捕まる確率が高いのにもかかわらず、なぜコンビニ強盗犯は実行に移してしまったのでしょうか。
様々なニュースを調べた結果、コンビニ強盗犯には共通するいくつかの心理や理由があることが分かりました。
最後に、過去にコンビニ強盗で逮捕された犯人の供述例を参考に、強盗する人の3つの心理・理由を解説します。
コンビニ強盗をする人の心理・理由①:お金が無くて困っているから
コンビニ強盗をする人の心理・理由1つ目は「お金が無くて困っているから」です。
その日に食べ物を購入するお金すら手元にない、当日までに借金を返済しなければならないなど、お金の面で窮地に立たされている人が強盗を実行に移してしまうケースがあります。
お金が目当てなので、店員に危害を加えるつもりはないかもしれませんが、犯人には精神的な余裕がないため店員が対応を間違えると、突発的な行動に出てくることも考えられるでしょう。
コンビニ強盗をする人の心理・理由②:家が近くて強盗しやすそうだったから
コンビニ強盗をする人の心理・理由2つ目は「家が近くて強盗しやすそうだったから」です。
実際に、同じ店舗で複数回の強盗を繰り返した犯人が捕まった際に、「家から近かったから」と理由を供述したケースもありました。
家から近いという理由だけで強盗されるのは店舗側も予測しようがないので、とにかくセキュリティを万全にするしかないでしょう。
コンビニ強盗をする人の心理・理由③:むしゃくしゃして衝動的にやった
コンビニ強盗をする人の心理・理由3つ目は「むしゃくしゃしていた衝動的にやった」です。
金銭が目的ではなく、何かに追い詰められて感情的に突発的な行動に出たパターンがこれに該当します。
犯人が強烈なストレスを抱えて犯行に及ぶ場合、店員が被害に遭うことも少なくないので、しっかり対策しておかなくてはなりません。
コンビニ強盗をすると懲役以上の判決が下される可能性が高い
コンビニ強盗をすると、懲役以上の判決が下される可能性が高いことをご存知でしょうか。
理由としては、刑罰以外にコンビニ側や被害にあった従業員個人から、民事的に訴えられるケースが多いからです。
記事の冒頭でも解説したように、コンビニ強盗は検挙率が非常に高く懲役以上の判決が下されやすいので、絶対に行うべきではありません。
コンビニ強盗の成功率や強盗が狙う時間帯や対応方法・対策まとめ
この記事では、コンビニ強盗の成功率や強盗が狙う時間帯、対応方法・対策について解説しました。
コンビニ強盗は店舗のセキュリティの高さや、レジからお金を盗みにくくなった時代背景から検挙率が上がっているので、発生件数は減少傾向にあります。
しかし、強盗犯が犯行に及ぶ理由は様々で予測ができないので、事前に万全の対策を備えておかなくてはなりません。
声掛けの徹底や、レジに大金を入れないといったお店の仕組み作りで対策できる部分もあるので、スタッフ全体の防犯意識を高めることも強盗対策の重要なポイントではないでしょうか。