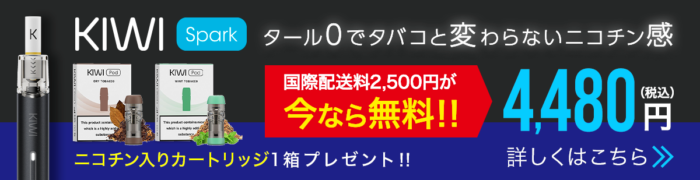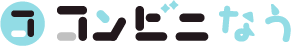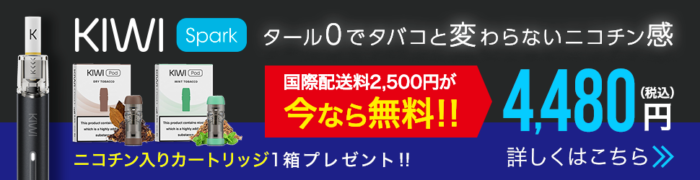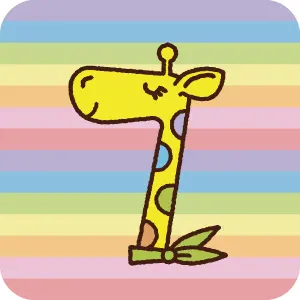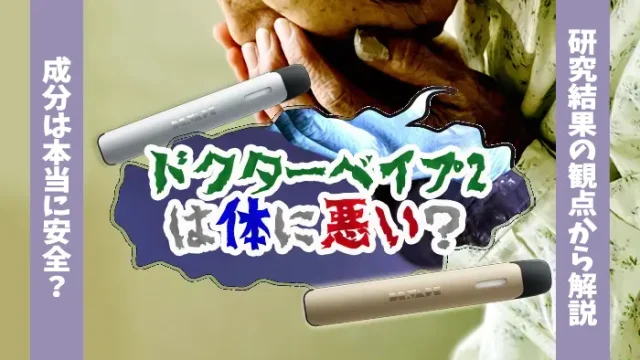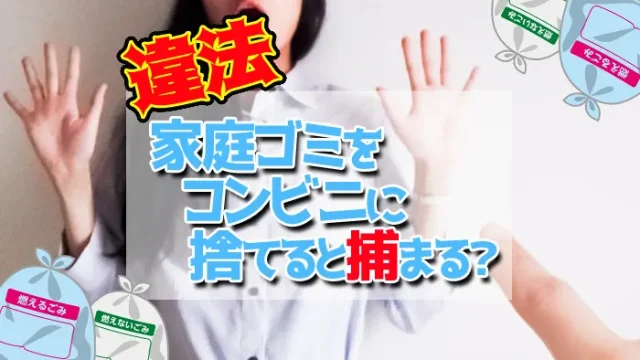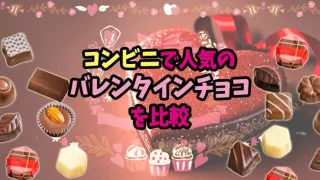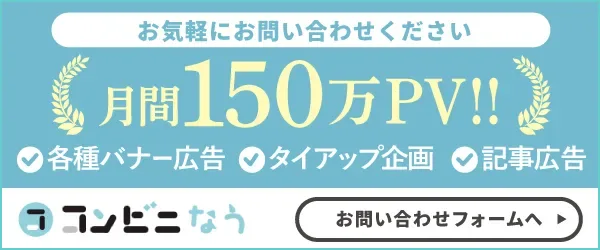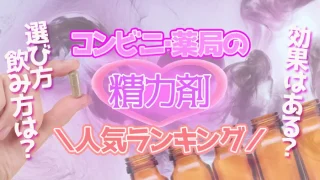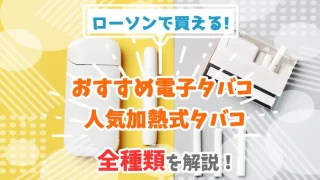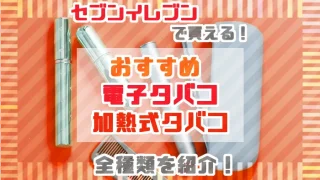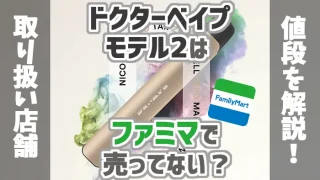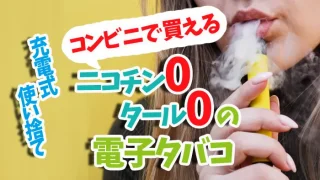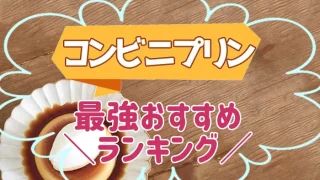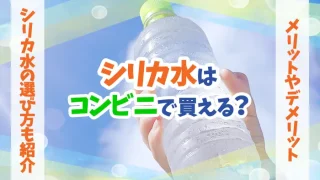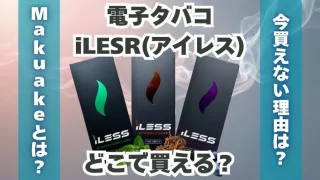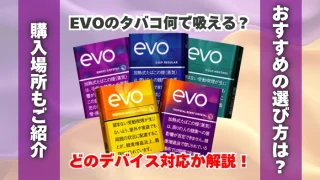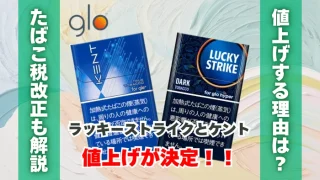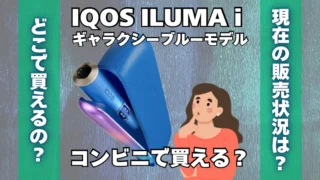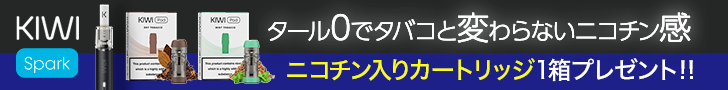ひな祭りは3月3日に行われる桃の節句で、女の子の健やかな成長や幸運をお祈りする行事ですが、ひな祭りが誕生した由来や歴史について詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではひな祭りが始まった由来や歴史に加えて、雛人形を出す・しまうタイミングや飾る場所についても分かりやすくお伝えします。
記事内ではひな祭りを家族でより楽しく過ごす方法などもご紹介しているので、興味のある方はぜひ参考にしてみてください!
目次
ひな祭りのほんとうの意味とは?怖い由来やなぜ雛人形を飾るのか分かりやすく解説
現代のひな祭りと言えば家族でお祝いする楽しいイベントのひとつですが、元々どのような由来や歴史があるのか、なぜ雛人形を飾るのかをご存知ない方も多いでしょう。
実はひな祭りの原点は子供の死が身近な時代に無病息災を祈る行事であったため、本当の意味を知ると少し怖いと感じる方も居るかもしれません。
まずは、ひな祭りの原型とされる流し雛の詳細や雛人形を飾る理由について解説していきます。
- 昔は子供の死亡率が高く「流し雛」の行事で成長が祈られていた
- 雛人形には「子供の代わりに災難を背負ってもらう」という意味がある
- 子供向けには「女の子の成長を祝う日」と説明されることが多い
ひな祭りの意味・由来①:昔は子供の死亡率が高く「流し雛」の行事で成長が祈られていた
昔は医療の未発達などを背景に子供の死亡率が高く、病気は「祟りや災いなどの邪気によるもの」と考えられていた時代がありました。
「流し雛」とは現代のひな祭りの原点となった行事で、桟俵(さんだわら)の舟に紙雛と椿の花・桃の小枝を乗せて邪気を川に流すことで、赤ちゃんの無病息災を祈ります。
子供の無病息災や健康長寿を祈る「流し雛」の文化と中国における「上巳の節句」の行事がひとつになったのが、現代まで受け継がれる「ひな祭り」の由来です。
ひな祭りの意味・由来②:雛人形には「子供の代わりに災難を背負ってもらう」という意味がある
ひな祭りの時期に飾られる雛人形には、子供の代わりに災難を背負ってもらうという意味合いが込められています。
つまり、人形が身代わりとなって厄災や災難を引き受けることで子供が無病息災・健康長寿となるようにお祈りするのが、ひな祭りに雛人形を飾る理由です。
雛人形を飾る場所を事前に空けておき、節分の豆まきを終えた後の大安の日に飾り始めると良いでしょう。
ひな祭りの意味・由来③:子供向けには「女の子の成長を祝う日」と説明されることが多い
流し雛を原点とするひな祭りの文化が生まれた背景には「子供の死が身近だった時代」があるため、現代の子供に意味合いを伝えるのは難しい部分があります。
「子供が死なないようにお祈りする日」と、ほんとうの意味を伝えると怖い思いをさせてしまうので、子供向けには「女の子の成長をお祝いする日だよ」と説明されるのが一般的です。
ひな祭りのほんとうの意味や歴史をちゃんと伝えるのは、女の子が少し大きくなってからの方が良いかもしれません。
ひな祭りの文化はいつから始まった?起源・歴史をご紹介
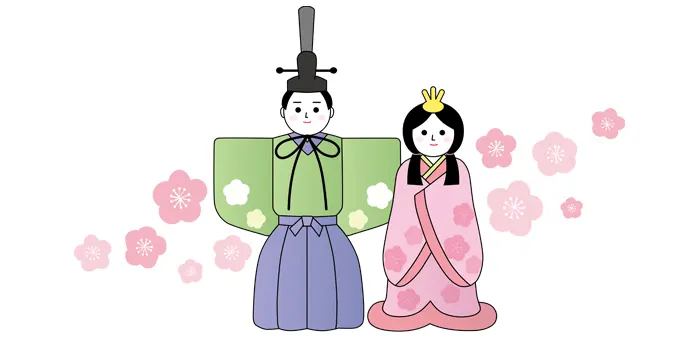
ひな祭りの歴史は奈良時代の日本にさかのぼり、中国の文化と日本の人形遊びの文化が結びつき、やがて雛人形を飾るスタイルへと変遷していきました。
流し雛の行事から発展した「ひな祭り」が庶民も楽しめる行事として広まったのは、江戸時代の中頃だと言われています。
ここからはひな祭りの起源や歴史の変遷、雛人形を飾る文化が世間に広まり定着した過程について確認していきましょう。
- 奈良時代に中国の「上巳の節句」の文化が日本に伝わった
- 上巳の節句と平安時代の「ひいな遊び」が結びつき文化として定着
- 江戸時代には「ひな祭り」という言葉で文化が広がっていった
- 最近は時代に合わせた雛人形が登場している
ひな祭り文化の起源・歴史①:奈良時代に中国の「上巳の節句」の文化が日本に伝わった
日本には人日・上巳・端午・七夕・重陽の「五節句」がありますが、五節句とは中国から奈良時代の日本に伝わった奇数が連なる日をお祝いする考え方のことです。
五節句のひとつである3月3日は上巳の節句と言われ、季節が変わる節目に女の子の無病息災や子孫繁栄を願います。旧暦の3月3日は桃の花が開花する時期であることから、上巳の節句は「桃の節句」とも呼ばれるようになりました。
ひな祭り文化の起源・歴史②:上巳の節句と平安時代の「ひいな遊び」が結びつき文化として定着
中国では上巳の節句に「形代(かたしろ)」「人形(ひとかた)」と呼ばれる紙の人形を体に当てて悪い気を移し、川に流すことで身を清めるという習慣があったそうです。
平安時代の日本では貴族の子が当時の高級品であった紙を使って、男女1組の人形遊びを楽しむ「ひいな遊び」が親しまれており、中国と日本の文化が合体してひな祭り文化として定着しました。
そこから日本でも「流し雛」の行事が行われるようになり、徐々に現在のような雛人形を飾って楽しむ文化へと変化していきます。
ひな祭り文化の起源・歴史③:江戸時代には「ひな祭り」という言葉で文化が広がっていった
江戸時代の中頃には紙人形の流し雛から飾り雛文化へと移り変わり、そこから「ひな祭り」という言葉が広まるようになりました。
当時は紙で作った立雛(たちびな)で人形遊びをするのが主流でしたが、京・江戸・大阪で「雛市」が開催されるようになり、衣装を着せた「座雛(すわりびな)」が登場したそうです。
また、雛人形を飾る場所である豪華な段飾りも、江戸時代に誕生したと言われています。
ひな祭り文化の起源・歴史④:最近は時代に合わせた雛人形が登場している
一般的な雛人形のイメージとは印象の異なる、時代に合わせたデザインの雛人形が登場していることをご存知でしょうか。
雛人形といえば一般的な日本人形の見た目をイメージしますが、最近では細眉で顎がすらっとした小顔タイプなど、現代の美的感覚が取り入れられた雛人形も誕生しています。
マンションなどは飾る場所が限られていることから、一段の平飾りになっている収納が簡単なタイプも用意されており、伝統的な雛人形の文化も時代に合わせて柔軟に変化しているようです。
ひな祭りの雛人形はいつからいつまで飾るの?出す日・しまう日がいつなのかを解説

ひな祭りの雛人形はいつからいつまで飾るのが正解なのか、出す日やしまう日が分からない親御さんも居るでしょう。
結論から言うと立春から桃の節句の一週間前までの大安の日に飾るのが良いとされていますが、ひな祭り前日・当日だけ雛人形を飾るのは「一夜飾り」と呼ばれ、縁起が良くないため注意してください。
ここからはひな祭りの雛人形を飾る場所にいつからいつまで出すべきかの具体的な日程と、飾る・しまう際の注意点について解説します。
ひな祭りの雛人形はいつからいつまで飾るのか:雛人形を出す日は「立春より後の大安」
娘のためにひな祭りゾーンを作りました✌️
— Bew(べう)💎 (@cos_Bew) February 13, 2023
2月の終わりになったら、本物の桃の花も飾る予定🌟 pic.twitter.com/5IoYDS8Tt7
雛人形は春に飾るので、雛人形を出す日は節分の翌日である立春より後の大安が良いとされています。
立春は「春の始まり」となる二十四節気のひとつで、節分の日に豆まきをして邪気払いを終えた後の大安の日が雛人形を出すのに一番良いタイミングです。
地域によっては二十四節気の「雨水(2月19日ごろ)」に飾ると良縁に恵まれると考えられているので、飾るタイミングに迷った時は親や親戚に聞いてみるのも良いでしょう。
2023年に雛人形を出す日一覧
- 2月7日(火)
- 2月13日(月)
- 2月19日(日)
- 2月23日(木・祝)
- 3月1日(水)
ひな祭りの雛人形はいつからいつまで飾るのか:雛人形をしまう日は「3月6日ごろ」
3月6日の「啓蟄(けいちつ)の日」は二十四節気のひとつで、「虫が春の訪れを感じて冬眠した土から出てくる」という意味合いから雛人形をしまうのに良い日とされています。
啓蟄の日に雛人形をしまうべきとされているのは、「雨水」から次の季節に移るタイミングであることや、暖かく湿気の低い日が多いことが主な理由です。
雨の日など湿度の高い時に雛人形をしまうと衣装などにカビが生えてしまう可能性もあるので、3月6日ごろの湿度の低い晴れた日にしまうのが良いでしょう。
ひな祭り前日・当日に雛人形を出す「一夜飾り」は縁起が良くないと言われている
前述しましたが、ひな祭りの前日や当日に雛人形を出す「一夜飾り」は縁起が良くない飾り方とされています。
雛人形は子供の厄災を引き受けて成長を見守ってくれる存在であるため、一夜飾りだけで済ませるのは失礼だと考えられていることが理由のひとつです。
また突然の訃報で一晩で準備するお通夜やお葬式を連想させることも縁起が良くない理由とされているので、雛人形を飾る場所は早めに決めて、短くとも2~3日は飾っておくのが良いでしょう。
ひな祭りの伝統的な食べ物や飾りについての7つの由来を分かりやすく解説

「ひな祭りに食べるもの」と聞いてひなあられやちらし寿司を連想する方も多いですが、伝統的な食べ物にそれぞれどのような由来や意味合いがあるのかを知らない方も居るはずです。
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りには女の子の健康や幸せを願う意味合いが込められているので、由来を知ることでさらに気持ちを込めて準備できるのではないでしょうか。
続いてはひな祭りの伝統的な7つの食べ物や飾りに込められた願いや由来を分かりやすく解説していきます。
- ちらし寿司
- はまぐりのお吸い物
- 甘酒
- 菱餅
- ひなあられ
- 桃の花
- ぼんぼり
ひな祭りの食べ物や飾りの由来①:ちらし寿司
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来や意味合い1つ目は「ちらし寿司」です。
ちらし寿司をひな祭りの日に食べる理由には諸説ありますが、「背が丸くなるまで」と長寿の願いを込めたエビや、「マメに働ける健康を」という意味で豆を混ぜるなど、縁起の良い食べ物であることが理由と言われています。
「寿」を「司る」と書くお寿司も元々縁起の良い食べ物として親しまれているので、家族全員の無病息災や幸運をお祈りしながら、ちらし寿司を食べてお祝いしましょう。
ひな祭りの食べ物や飾りの由来②:はまぐりのお吸い物
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来・意味合い2つ目は「はまぐりのお吸い物」です。
ひな祭りにはまぐりを食べる習慣は平安時代の貴族が行っていた「貝合わせ」が由来とされており、貝殻の内側に絵を書いてトランプの神経衰弱のように同じ絵柄を探す遊びが行われていました。
貝殻は同じ組み合わせが存在しないことから、夫婦円満の象徴として結婚式やひな祭りの食べ物として出されるようになったと言われています。
ひな祭りの食べ物や飾りの由来③:甘酒
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来や意味合い3つ目は「甘酒」です。
上巳の節句では「邪気を洗い流し厄払いするため」「健康長寿を祈って」白酒を飲む習慣がありますが、当然ながらアルコールが含まれているので子供は白酒を飲めません。
そのため子供も飲めるようにと誕生した「甘酒」は、主に麹や酒粕で作られており、美容にも良いため女性をお祝いする日に最適な飲み物と言えるでしょう。
ひな祭りの食べ物や飾りの由来④:菱餅
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来や意味合い4つ目は「菱餅(ひしもち)」です。
ヒシの実をモチーフにした菱餅の形は尖っていることから魔除けになるとされ、繁殖力の強いヒシの特徴からは「子孫繁栄や長寿を願う」という意味合いが込められています。
桃・白・緑色にもそれぞれ異なる意味や願いが込められていることからも、菱餅は「女の子の健康や子孫繁栄を願う」という意味合いが何重にも込められている食べ物と言えるでしょう。
ひな祭りに食べる菱餅の色の由来
| 菱餅の色 | 意味 |
|---|---|
| 緑 | ・植物のエネルギー ・健やかな成長 |
| 白 | ・雪(大地)のエネルギー ・長寿や子孫繁栄 |
| 桃 | ・血(生命)のエネルギー ・魔除け |
ひな祭りの食べ物や飾りの由来⑤:ひなあられ
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来や意味合い5つ目は「ひなあられ」です。
ひなあられは元々菱餅を小さく小分けにして作られたのが由来とされ、ひなあられも菱餅と同じ緑・桃・白色の3色で構成されていることがその根拠と言えるでしょう。
4色で構成されたひなあられの場合は「四季のエネルギーを得られるように」「1年を通して幸運が運ばれますように」といった意味が込められています。
ひな祭りの食べ物や飾りの由来⑥:桃の花
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来や意味合い6つ目は「桃の花」です。
上巳の節句が行われる頃に桃の花が開くことと、中国では桃の花が邪気払い・不老長寿・子孫繁栄をもたらす仙木と考えられていることから、ひな祭りに桃の花を飾るようになりました。
室町時代では、大人は桃の花びらを浮かべた桃花酒を飲むことで悪い気を払い、無病息災を願ったと言われています。
ひな祭りの食べ物や飾りの由来⑦:ぼんぼり
ひな祭りの日に出される食べ物や飾りの由来や意味合い7つ目は「ぼんぼり」です。
ぼんぼりは懐中電灯のような役割を持つ小型の行灯(あんどん)のことで、電気が無い時代に夜道の足元を照らす明かりとして使用されていました。
雛人形の文化が広まった江戸時代の結婚式は夜21~23時ごろに行われるのが一般的で、ぼんぼりが必須だったことから、雛人形と一緒に飾るアイテムとして使われるようになったと言われています。
ひな祭りをより楽しむための3つの過ごし方を紹介!

ひな祭りは子供の健康を祈って行う行事ですが、何より家族みんなで楽しく過ごしたいイベントでもあります。
子供が主役の行事なので雛人形を出す準備などの段階から一緒に参加できるようにすると、さらに楽しいひな祭りになることでしょう。
ここからはひな祭りを家族でより楽しむための3つの過ごし方を紹介していくので、お子様が喜びそうな方法があればぜひ取り入れてみてください!
- ちらし寿司やケーキでお祝いする
- 雛人形を飾ったり雛飾りを作る
- ペープサート(紙の人形劇)やクイズで由来を伝える
ひな祭りを楽しむための過ごし方①:ちらし寿司やケーキでお祝いする
家族でのひな祭りがさらに楽しくなる過ごし方1つ目は、ちらし寿司やケーキでお祝いすることです。
大人と子供で力を合わせてちらし寿司の具材を切ったり混ぜたりしながら、具材に込められた意味合いをクイズにして教えてあげるのも楽しい時間になるでしょう。
ひな祭りの時期には可愛いお人形が乗ったデコレーションケーキが販売されるので、ちらし寿司を食べ終えた後にみんなでケーキを食べて過ごすのもおすすめです。
ひな祭りを楽しむための過ごし方②:雛人形を飾ったり雛飾りを作る
家族でのひな祭りがさらに楽しくなる過ごし方2つ目は、雛人形を飾ったり雛飾りを作ることです。
雛人形を購入しているのであれば「お殿様が左でお雛様が右だよ」と配置を教えてあげて、飾り付けを一緒に手伝ってあげると喜ばれるでしょう。
折り紙や紙粘土のつるし雛で雛飾りを一緒に楽しむのも盛り上がるので、ぜひお子様と一緒に作ってみてください。
ひな祭りを楽しむための過ごし方③:ペープサート(紙の人形劇)やクイズで由来を伝える
家族でのひな祭りがさらに楽しくなる過ごし方3つ目は、ペープサート(紙の人形劇)やクイズでひな祭りの由来や歴史を伝えることです。
ひな祭りの由来や雛人形に込められている願いごとの意味を、言葉だけではなくペープサート(紙の人形劇)で物語形式にして伝えてあげると小さなお子様にも喜ばれます。
ちらし寿司の例でも紹介しましたが「ひな祭りは昔どうやってたと思う?」「ひな祭りのお花が何か知ってる?」とクイズ形式で伝えてみるのも面白いのではないでしょうか。
ひな祭りや雛人形に関する3つの質問に回答

ここまでひな祭りの歴史や起源や雛人形に込められた意味に加えて、ひな祭りの食べ物や飾りの由来などを解説してきました。
ひな祭りについて知る内に「雛人形を飾る場所はどこ良い?」「雛人形を飾る年齢はいつまで?」といった疑問が出てきた方もいるのではないでしょうか。
最後にひな祭りや雛人形に関する3つの質問に回答していくので、より深くひな祭りについて知りたい方はぜひチェックしてみてください。
- 雛人形を飾る場所はどこがいい?
- 雛人形を飾る年齢はいつまで?
- 雛人形を処分する時はどうすればいい?
ひな祭りや雛人形に関する質問①:雛人形を飾る場所はどこがいい?
雛人形を設置するスペースを確保できない場合はタンスやキャビネットの上でも大丈夫ですし、玄関に雛人形を飾られる方もいます。
いずれにしても、雛人形は子供の無病息災を願う大切なお人形なので、たくさんの人に見てもらえる場所が良いでしょう。
飾る場所は基本的にどこでも大丈夫ですが、直射日光が当たる場所だとお人形の顔がひび割れてしまったり、衣装が色あせてしまうので注意してください。
ひな祭りや雛人形に関する質問②:雛人形を飾る年齢はいつまで?
「雛人形を何歳まで飾ってあげるべきか」と悩む親御さんは多いですが、結論を言うと特に決まりはありません。
年齢の決まりがないからこそ悩む部分もあるかと思われますが、考え方としては子供が独り立ちしたと感じた時がひとつのポイントになるでしょう。
例えば進学時に実家を離れて入寮・留学する時や就職で一人暮らしを始める時、結婚してパートナーと生活をスタートするタイミングなど、人生の節目で雛人形を飾らなくなるご家庭が多いようです。
ひな祭りや雛人形に関する質問③:雛人形を処分する時はどうすればいい?
日本人特有の感覚なのか、人形やぬいぐるみを捨てるのに心理的な抵抗を覚えるという方は少なくないでしょう。
自治体のルールに従ってゴミとして処分することは可能ですが、そのまま捨てるのは忍びないので、大切な人形を供養する気持ちを表すために和紙などで包み塩を振る方もいます。
飾らなくなった雛人形はお寺や自治体のリサイクルセンターに持ち込むほか、寄付をしたり専門店に売却する方法などもあります。
しかし、雛人形には「子供の厄災を肩代わりする」意味合いがあるため、知人などに一方的に譲ろうとするのは避けるべきです。
ひな祭りの由来や歴史とは?雛人形はいつからいつまで飾るのか出す日・しまう日や飾る場所まとめ
この記事ではひな祭りの由来と歴史のほか、雛人形をいつからいつまでどこに飾るのかについて詳しく解説しました。
雛人形を飾る場所や出すタイミングは基本的に自由ですが、前日や当日だけの一夜飾りは縁起が良くないので、少なくとも2~3日以上は飾っておいた方が良いでしょう。
ひな祭りに出す食べ物や飾りの由来や歴史を教えたりしながら、女の子の健康と幸せを願って家族で楽しく過ごしましょう!